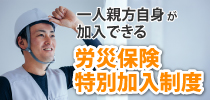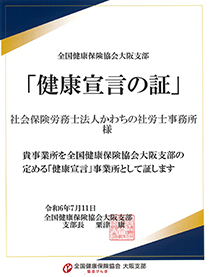会社を辞めると、社会保険の加入状況が変わるため適切な手続きを行うことが重要です。
今回は、会社を辞めたらどうなる?退職後の社会保険制度について解説します。
社会保険(健康保険)
退職後は会社の社会保険(健康保険)を脱退するため、新しい社会保険の加入先を決めなければなりません。主に以下の3つの方法があります。
1. 社会保険の「任意継続」
会社で加入していた社会保険を引き続き利用できる仕組みで、会社の社会保険と同じ保障を受けられるメリットがあります。
ただし加入期間は退職後2年間となり、また、会社負担分がなくなるため、保険料は全額自己負担となります。
2. 国民健康保険に加入
社会保険の任意継続をしない場合、市区町村の社会保険である国民健康保険に加入します。
保険料は世帯全体の収入によって決定されるため、退職前の収入が高い場合、翌年の負担が増える可能性があります。
住んでいる自治体で、退職後の保険料の試算をしてみるのも良いでしょう。
3. 家族の社会保険に加入
配偶者など、家族が会社の社会保険に加入している場合、その扶養に入ることも可能です。
国民健康保険や社会保険任意継続よりも費用が抑えられるなどのメリットがありますが、退職後の年収は130万円未満とするなどの条件があります。
国民年金の手続き
退職すると社会保険の厚生年金加入資格を失うため、自分で手続きをする必要があります。
1. 国民年金に加入
会社員時代は厚生年金でしたが、退職後は「国民年金」に切り替わります。
20歳以上60歳未満の人は、社会保険の一環である国民年金保険料を支払う義務があります。
令和6年度における保険料は月額約17,000円ですが、収入が減り支払いが厳しくなる場合は「免除」や「猶予」などの制度もあります。
2. 配偶者の社会保険の扶養に入る
配偶者が社会保険の厚生年金に加入している場合、「年収130万円未満」の条件を満たせば第3号被保険者になり、社会保険料の支払いが不要になります。
失業保険(雇用保険)の手続き
退職後、一定の条件を満たせば社会保険の一部である失業手当を受給できます。
受給資格
退職前の2年間に「雇用保険に12カ月以上加入」しており、ハローワークで求職活動をしていることなどの条件があります。
受給までの流れ
退職後、ハローワークで「求職申込」を行い、7日間の待機期間を過ぎたあと失業認定を受けることになります。
ただし、自己都合退職の場合は3カ月間の給付制限があります。
—————–
このように退職後の社会保険にはいくつかの選択肢があります。
退職後の各手続きには期限があるため、早めに準備し、自分に合った社会保険の選択をしましょう!