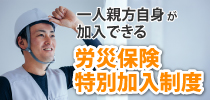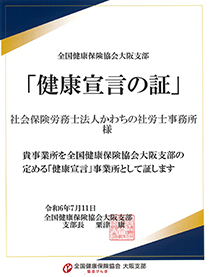過労死防止学会誌抜粋 ←クリックすると画像が見られます
2024年夏に開催された過労死防止学会第10回大会の分科会において、「社会保険労務士がとりくむ過労死防止活動~過労死防止法制定後、10年連続で講演会を開催~」と題して発表しました。
私が代表幹事を務める 大阪府社会保険労務士会 安全・衛生自主研究会の活動を振り返るとともに、過労死防止運動に社会保険労務士がどうとりくむかを論じました。
このほど過労死防止学会誌が発行され、発表した内容が掲載されました。
以下に提言部分を紹介します。(全文は上記の抜粋をご覧ください)
6.社労士にもできる過労死防止活動
①過労死防止月間の過労死防止シンポジウムに参加する:
ここ数年、11月に開催される過労死等防止対策推進シンポジウムに大阪だけでなく近県にも参加しました。㋐大阪は参加者数がコロナ前の半分以下になっており、回復できていない㋑兵庫は大阪に匹敵する参加者数を確保し、兵庫県社労士会が後援団体に参加している㋒奈良は参加者数は少ないが労働組合が積極的に関わっている、という印象を受けています(図表2 参照)。 社労士の参加を促すためにも、都道府県社労士会の後援団体としての参加が重要だと思われます。今のところ、社労士会が後援団体になっているのは兵庫県・新潟県だけのようです。もっとも、その前に都道府県弁護士会の後援(こちらも多くはない)が重要との指摘もあります。
図表2 過労死等防止対策推進シンポジウム 府県別/年度別参加者数
| 府県/年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 大阪府 | 140 | 186 | 195 | 181 |
| 兵庫県 | 83 | 149 | 194 | 192 |
| 奈良県 | 61 | 96 | 30 | 62 |
※下線部は筆者が参加したシンポジウム
②各種団体に積極的に参加する:
過労死防止センター・過労死家族会・過労死防止学会、労働NPOなど、門戸は開かれています。社労士に対する認知度は低いか、マイナスイメージを持たれているとしても、積極的に参加すれば歓迎され、見方も変えていけるでしょう。
③過労死防止啓発授業の担い手として参加する:
現在の過労死防止啓発事業の担い手は当事者(遺族)・学者・弁護士となっています。社労士が担い手として参加するには、ある程度の知見が必要と思われ、「てびき」があると心強いと感じます。神奈川県の「共通教材」づくりの提起に賛同します。
④社労士会の学校教育特別活動「出前授業」を改善する:
出前授業に関しては、社労士会の「社会貢献活動(学校教育特別部会による)」が過労死防止センターのとりくみを量的に上回っています。 社労士会の出前授業の内容は、テキストをもとに「給与明細の見方」など社会人として働く初歩を講義するものですが、テキストには顧問社労士が職場に突如現れて、労働者たちにアドバイスするという“ありえない”設定の漫画も使われています。現実は事業主に雇われている社労士が直接従業員からの相談に応じることなどないからです。
社労士会の「出前授業」テキストに過労死防止を盛り込むことで、出前授業の内容が改善され、「会社貢献」から真の「社会貢献」につながると考えます。
7.社労士ならではの過労死防止活動とは
①関与先企業に対して:
給与計算や労働保険・社会保険の手続業務などは、企業にとっては単なる「アウトソーシング」であっても、社労士が労働時間管理などに日常的に関わる機会となります。企業がコンプライアンス(法令遵守)のために社労士に顧問を依頼しているのなら、なおさら労働時間管理やハラスメントについてのアドバイスができます。
②個人の相談者に対して:
障害年金の相談では、「労災」が疑われる事例が多く、精神疾患の場合は「もっと早く(病状が固定する前に)相談に来てくれれば」と思うことがしばしばあります。 労働相談では、社労士だけで解決できないことも多く、相談者のニーズに応じて、弁護士や労働組合につなぐことが大切になります。
③社会保険労務士法に立ち返って:
冒頭に記載した社会保険労務士法第1条(目的)について、私のこれまでの理解は、企業と労働者のどちらの立場にも立てる社労士の資格を生かして、㋑企業をサポートするときには労働トラブルの防止、メンタルヘルスの発生防止、過労死防止などにつながる仕事を心がける ㋺労働者や年金受給希望者の相談にも積極的に応じるというふうに、やや図式的に捉えていました。
現時点では、企業も人間と同様、何歳になっても発達できる(人格の発達に完成はない)し、生まれ変わること(自己変革)もできる。「事業の健全な発達」には、会社はどうあるべきかを追求していくことが含まれる。株主や経営者だけでなく、従業員、消費者、コミュニティ、環境などの「ステークホルダー」に貢献することも含まれる。とりわけ従業員(労働者)の幸福を大切にすることが重要だと考えています。
昨今、コンプライアンス(法令遵守)以上に「ビジネスと人権」が喧伝されています。ビジネス(儲け)のための人権尊重ではなく、労働者の人権を大切にする中小企業を増やし、サポートしていきたいと思います。