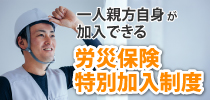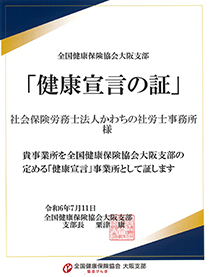かわちのタイムスNo.73(20250201) ← クリックすると画像が見られます
【1面】
センター設立から2年経て
労働保険事務組合の認可を申請
「一般社団法人かわちの労災保険センター」の第3回総会が12月5日に開催され、9名が出席しました。
この総会をもって、センター活動実績が2年間に到達。会員数も30名を大きく超えている(現在44名)ので、労働保険事務組合の認可の条件をクリア。1月までに大阪労働局事務組合課に「労働保険事務組合」認可申請を行いました。2月の実地調査を経て認可される見込みです。
【今後のプログラム】
◆認可決定(4月1日)
◆「大阪SR経営労務センター」会員様の「かわちの労災保険センター」への委託替え
◆労働保険料年度更新(4~5月)
▽R6年度の確定保険料計算…SR経営労務センター
▽R7年度の概算保険料計算…かわちの労災保険センター
◆第4回かわちの労災保険センター総会(5月17日)
◆労働保険料・会費納入
労働保険事務組合を利用されているお客様には、振替口座の変更などお手間を取らせることになりますが、「かわちの労災保険センター」の運営に何卒ご協力ください。
また、事業主・家族も入れる労災特別加入を利用されていないお客様は、この機会にぜひ加入をご検討ください。
ヘビーな年を乗り切り、中小企業の地域のセンターとなる労働保険事務組合をスタートさせたいと考えています。
かわちの労災保険センター 第3回総会(2024.12.5)

2025年のテーマ
ヘビーな年になりそう? 巳も心も柔軟に乗り切ります。
開業めざす社労士に「介護処遇改善」講義

制度がコロコロ変わるので気分転換になるかも?
本棚
『セブン元オーナーはなぜ闘ったのか 日本のコンビニを問う』 (旬報社)
東大阪市のセブン・イレブン南上小阪店元オーナー・松本実敏さんの闘いの記録。
裁判に負けても、コンビニ時短問題を世に知らしめ、コンビ二の世界全体に与えた影響は計り知れない。私も「支援する会」に参加しました。
【2面】
年金よろず相談 八ノ巻・下
受診歴のない障害年金
〔3ヵ月たったお彼岸の頃〕
社労士 お世話になります。かくかくしかじか、お聞きのとおりの状況ですので診断書を作成していただけますか。
医 師 検査結果があるだけで受診したことがないと。診断書を書く材料として、子どもの頃のことを証明できるものがあるといいのですが。
社労士 「引きこもり」で家事もさせたことがないので、何がどの程度できるか、母親にもわかりません。保育所には通えていたので、その辺を探ってみます。
〔それから数カ月後〕
社 長 H子の母親に聞いたら、「年金が振り込まれていた」いうので、慌てて電話しました。
社労士 良かったですね。年金証書や支給決定通知を見ても、「何のことですか?」という人が多いので。
社 長 正直、2級に通るのかな?と思ってたわ。
社労士 診断書がよかったので、予想はつきました。保育所の元担任の保育士さんから聴き取りしたエピソードなど、ほぼそのまま診断書に盛り込んでもらえたので。
社 長 母親も何とか働けそうやし、子どもの「ひきこもり」も何とかせな。
社労士 今回のことで、社長さん始め H子さん親子のことを親身に考えてくれている人が周りにいることがわかりました。若者の自立を支援している人とか、つながりを生かしていけたらと思います。これからもお困りの人がいたら何なりとお聞きください。
※ このコーナーは実際に寄せられた相談をモデルにしたフィクションです。
だから映画はおもしろい vol.61
港に灯(ひ)がともる
(2025年、日本)
●阪神淡路大震災から30年の今年、「その街の子ども 劇場版」の映画を見た1月13日夜に日向灘地震が起こり、南海トラフ地震の恐怖がよぎりました。そして、1・17の翌日に本作を観賞したので、地震が頭から離れない1週間になってしまいました。
●「心の傷を癒すということ 劇場版」で精神科医から見た震災を描いた安達もじり監督が、“心のケア”をテーマに神戸を舞台にした映画を作りました。制作会社の「ミナトスタジオ」と主人公の名前・灯(あかり)をくっつけたようなタイトルです。
●「その街の子ども」などこれまでの震災を描いた映画と違って、主人公の金子灯(富田望生)は震災の翌月に生まれた在日コリアン三世です。被災の記憶も在日の自覚もない灯は、父(甲本雅裕)や母(麻生祐未)が口にする家族の歴史や震災当時の話が遠いものに感じられ、孤独と苛立ちを募らせます。「全部しんどい」と苦しむ灯。さらに姉が持ち出した日本への「帰化」問題で家族は対立し、灯は心の病気になってしまいます。
●患者同士の対話によるクリニックの治療、転職先の人たちや仕事でつながった商店街の人々と関わることで灯の苦しみ、生きづらさは徐々に和らいでいきました。離れていた父とも何とか対話ができるようになりました。
●人々が寄り添い、傷ついた人が心を癒すことのできる社会になっているか。そうでなければどうやって変えていくか。それが本作のテーマではないかと思います。
編集後記
▼「正月は花園で」が高校ラグビーの合言葉。元日、自宅から自転車で行ける花園ラグビー場で50年ぶりに観戦しました。熱戦に若き日を思い起こしました。
▼派遣や日々紹介で働く労働者の労災事故が目立ちます。はやりの「スキマバイト」では労災保険が使えないかも。
まさに労働法のスキマをつく働かせ方といえます。